<11>向島奇譚
- 2003.07.01
- column
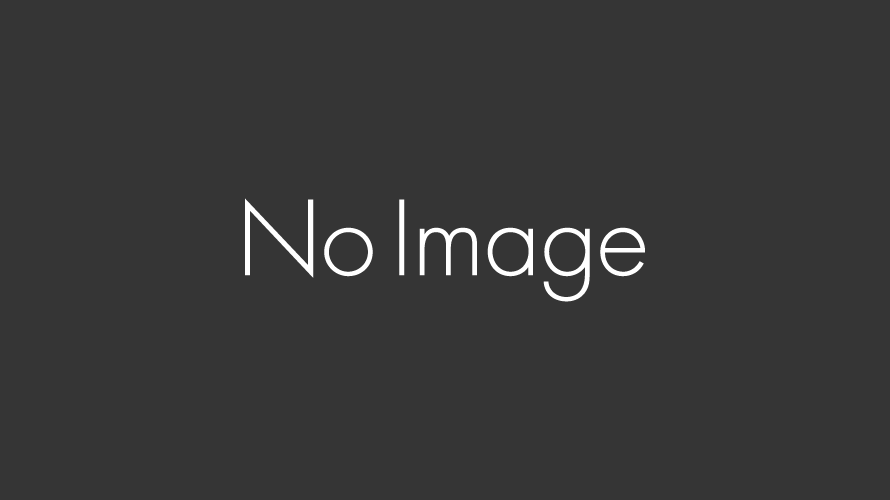
先日、例によってライブの後、終電をのがし、帰宅できなかった。そういう時えてして、たやすく異界空間に入り込みやすく、2、3日その状態をひきずるものだ。
結局知人宅にて仮眠はしたものの、その後あっさり帰宅するのも、別に誰にとがめられるわけでもないのにバツがわるく、知人S氏をとにかく亀戸へ行こう、とお誘いした。S氏はワケも聞かずに(そも、ワケがないのだが)、行こう、と答え、我々はわざわざダイダイ色の列車といくつか乗り継いで亀戸へついた。
そしてかの亀戸ぎょうざを食した。
それからなぜだか、また別の電車にのり、曳舟という駅名に惹かれて下車した。
そしてへらへらしながら路地へ路地へとくねくね歩いていたら、細くて真直ぐな道へ出た。通りには見渡す限り、我々ふたりと、向こうの方にひとりいるだけ。その向こうから来る人がだんだん近付くにつれ、なんだか知ってる人と似た背格好だと思ったが、果たして、本当にその、知っている人その人だった。
なぜだ。
しかも私もS氏もその人をよく知っているのだった。3人とも、なんでこんなに三人の誰もが住まいも仕事のフィールドも全く曳舟とはほど遠いのに、その駅でもないただの路地で、たった今、路上に3人しかいないその3人なのか。
ひとしきり3人で気味悪がって、ではまた、と別れた。
S氏とまたたらたらと歩き出すと、妙に惹かれるたたずまいの小さな小さな飲み屋を見つけた。
S氏と私は同じタイミングで目配せし、ここだな、と意を交しあったが、覗いたところまだ開店前と見えた。小いち時間してまた同じところを通ってみると、客らしいおじさんと大きなゴールデンレトリバーがお座敷カウンターで飲んでいて、よしとばかりに『お店は何時からですか。』と聞いた。
すると、『あらごめんなさい、お店、もうやってないのよお。でもお茶くらい入れたげッから飲んできな。』と云う。
我々は遠ざかりかけた足を戻して、え、そう?という顔ですごすご靴を脱いであがった。レトリバーが熱列歓迎してくれた。
お茶を入れてくれるのだと聞いたが、『何飲む?ビールだね。』と、すごい勢いでビールをついでくれた。我々はポカンと流れに飲まれるのだった。そしてS氏も私もつがれるままに飲んだ。
ひとしきり世間話をした後、おじさんは隣部屋(と云っても区切りはないが)ですやすや寝てしまい、おばさんはなにやらそうめんを茹でている。
おばさんは筑波の生まれで、千住に出てきて、芸者をやっていたそうだ。三味線と唄を習得し、その後この店をまかされた。女一人で時にはやくざと渡り合い、この世の事はたいてい見てきた風であった。町内の困り事やケンカの仲裁はもっぱらおばさんの役目になっているらしい。70手前と云ったところか。少し前に店を閉めたのだそうだ。今は夜中の2時の迎えの車にのって、築地の市場で朝まで働いているそうだ。
そのうち2階から別のおじさんが降りてきて、そのまま縁側方面へ出て消えていった。そうかと思うと、近所のおじさんらしき人がステテコ姿でやってきて、どこの誰さんのお姉さんがそろそろ危ないからよろしくたのむ、と云って出ていった。
S氏は気付くといつの間にか特大グラスに焼酎ロックを並々つがれて、それをいく杯も飲んだらしく、そのうち何を聞いても幸せそうにケタケタ笑うだけになってしまった。ゆでとうもろこしや、自家製うめぼしや、たらの身の塩煎りのようなのをいただき、向こうから猫までやってきた。
レトリバーは子供の頃にもらってきた飼い犬だが、猫はもともと近所の飼い猫だったのにおばさんのところに居着いて、帰らなくなってしまったそうだ。レトリバーと猫とS氏は三つ巴にぴったりくっついて寝入ってしまった。それを見ていてつい私も横になっていた。
気付くと5時間かそこらたって、もうすっかり日が暮れていて、我々は酔いざめに暖かいそうめんをすすって、そこを後にした。お金は要らないよっ、と怒ったようにおばさんは云って、またおいでね、と云ってくれた。
我々は不思議な気分でまたたらたらと駅へ戻り、電車にのった。
<11>
-
前の記事
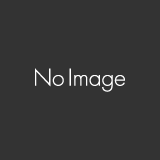
<10>膝小僧とおでんの匂い 2003.06.14
-
次の記事
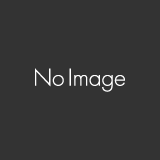
<12>真夏の一日 2003.08.10
