<76>とうもろこしの時間
- 2014.06.26
- column

昨年、10ヶ月間ほど、同居人がいた。
当初、『ワタクシごとではあるが同居人ができた』とコラムに書いたら、そのせいで(と思いたい)、それまで飲みに誘ってくれた人々からの誘いが、ピタっと途絶えた。その後、『亜紀ちゃん、やっと、おめでとう』と、私の将来を案じてくれていたらしい年上女性たちに、お皿だとか何だとかとにかく、‘ペア’ のものを頂くことが数回あった。
けど、同居人は女だった。
私よりうんと年下なのに、うんと背が高く、理系で、繊細ではあるが繊細でもない風に、状況をみてふるまえる女だった。繊細さを売りにして威張るオトコと暮らすより(そんなオトコがいるとして、の話ね)、ぜんぜん穏やかで、たんたんとした日々だった。
ちゃんと恋愛のようなものもしているらしく、近く同居する予定なので、それまでの間置いてほしい、とのことだった。朝早く会社へ出かけ、夜遅く帰ってくるので、必然的に食事だとか洗濯だとか、私がやることが多かったが、彼女の下着など干すときに、『恋をしている女の下着ってか』とちらっと思ったりした。アタシなんか、ユニクロの機能とお値段重視のものばっかし。
年が明けると同時、彼女は新しい『愛の巣』へ旅立っていった。そして、半年ほど経った今日、段ボール一杯のとうもろこしを送ってきた。開けると、いかにも新鮮な産毛を気もちよさそうに生やした葉に、大事そうにつつまれたツヤツヤの黄色だった。
きみどり色の、柔らかくビニルみたいなヒゲを、どうしてこんなに美しいのかと思いながらむしって、生で食べた。
3ヶ月前、父が死んだ。
父は北海道生まれで、偶然だが私が知らせを受けたのも北海道ツアー中だった。末っ子で、とてもかわいがられた、という自覚がある。父の故郷の北海道を共に旅した回数も、家族の中で私がいちばん多い。
小学生のとき、その父が共に訪ねた北海道の屋台で、とうもろこしを買ってくれ、前歯でかじっていた私に、こうやって食え、と、公園で、親指でひとつひとつそぎ落としてみせた。その手つきに妙に感動したことを、今でも覚えている。そうやって食べると、奥歯で食べられるから前歯の間に挟まらないし、粒の根元まできちんと食べられる。これは画期的な食べ方だと小学生なりに思った。
台所に立ったまま、父みたいに、ひとつひとつそぎ落としながら、ふと、二人の兄たちは、父とそんなやりとりをしたことが果たしてあったのだろうか、などと一瞬考えた。まあ、あるのだろうけど。
元同居人の送ってくれたとうもろこしは、北海道産ではなく、私の出身地、静岡県産のものだったが、それはとても甘くて美味しかった。同居中、会話の8割は、食べ物に関することだったように思うが、そんな中から、彼女としてもコレは絶対私が気に入ると確信があったのだろう、と思う。
夜になって、自宅でゆっくり吟味するため、実家から持ち帰ってきていた父の遺品を、少し整理しようという気になった。
父の肌着が出て来た。気に入るとそればかり着る人だったので、すり減って穴があいたところを、母が縫い繕ってあった。その繕い方が、実に入念で思わず笑ってしまった。
この3ヶ月、バタバタしていて、あっという間に過ぎた。ふと気づくと、いったい父は、今、どこで何をしているんだろう、と考えているのが可笑しい。
この世的には、いわゆる『変人』と云っても過言ではない人だったと思うが、あのとうもろこしの時間の『ふつうの人』さが、安堵と共に蘇ってくる。

<76>
-
前の記事

<75>Q&A『よくある質問』その2 2014.03.17
-
次の記事
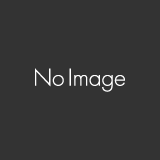
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2014 in EZO、出演決定! 2014.07.10
